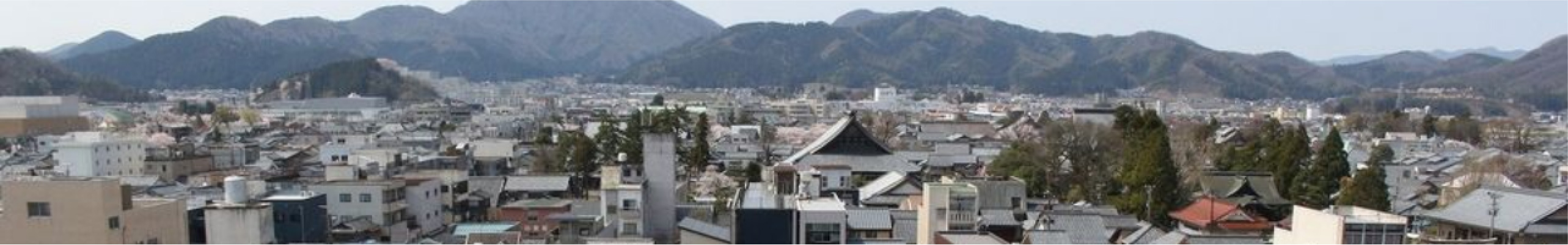最終更新日 2025年4月7日
家屋の固定資産税について
PAGE-ID:528
家屋の課税
税額の求め方
- 固定資産税額=課税標準額×1.4パーセント
- 都市計画税額=課税標準額×0.2パーセント
家屋は固定資産税・都市計画税ともに、評価額が課税標準額となります。
家屋の評価
家屋の評価は、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に基づき、再建築価格を基準に評価しています。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
評価額の算出方法
- 新増築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
経年減点補正率とは、 家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況を再建築価格に反映させる補正率です。 - 在来分家屋の評価
評価額=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率
再建築費評点補正率とは、物価の変動を考慮した補正率です。
在来家屋の場合、家屋の評価額の見直しは3年ごとに行っています(直近の基準年度は令和6年度)。 見直した評価額が前年度の評価額を超えるときは、前年の評価額に据え置かれます。
また、家屋の構造・用途ごとに定められている経年減点補正率が、20%に対応する年数を経過する場合には全て20%に止めることとされていますので、建築から相応の年数が経過した家屋については、評価額が下がらないことがあります。
家屋所有者
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人になります。
基準日である1月1日時点の所有者に、その年の固定資産税・都市計画税が課税されます。
家屋所有者の変更
登記されている家屋は、法務局で「所有権移転登記」をしてください。相続、売買、贈与、持分移転、保存等の種類があります。
詳しくは、法務局へお問い合わせください。
登記されていない家屋は、新たに登記を行うことが義務付けられています。
表題登記の手続きを行うとともに、年内に登記が終わらない場合、市役所に次の書類を提出して変更手続きをしてください。
<必要書類>
- 家屋補充課税台帳所有者変更届
家屋補充課税台帳所有者変更届(ワード形式 41キロバイト)
家屋補充課税台帳所有者変更届(PDF形式 97キロバイト) - 印鑑証明書(原本)
…新・旧所有者の双方が提出してください。相続の場合は相続人のみ提出してください。 - 変更の原因を証する書類(写し)
…相続は「遺産分割協議書」、売買・贈与は「契約書」、競売は「売却許可決定通知書」、等
所有者の変更は、手続きの原因日に関わらず、手続きが完了した年の翌年からとなります。
新築住宅の減額措置
新築住宅には、固定資産税がかかることになった年度から3年間(3階建て以上の中高層耐火建築住宅は5年間)、床面積の120平方メートルまでに相当する固定資産税の税額が2分の1に減額されます。
都市計画税には新築住宅の減額措置の適用はありません。
減額の対象となる住宅は、次の要件に該当する住宅です。
- 専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(その家屋の一部が居住の用に供されている家屋)で、居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上のもの
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの
また、長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅の場合は、減額期間が2年間延長されます。
家屋を建築する前の「長期優良住宅建築等計画の申請書」等は、丹南土木事務所へ提出してください。
家屋を取り壊した場合
固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日現在の状況で課税されます。
年内に家屋を取り壊された場合には、家屋滅失届を税務課、今立総合支所、味真野出張所または白山出張所にご提出ください。
現場を確認した上で、次年度より課税台帳から抹消いたします。また、電子による申請を行うこともできます。
なお、登記がされている家屋を取り壊された場合には、管轄の法務局に建物滅失登記をしていただく必要がございます。
滅失登記の詳細につきましては管轄の法務局へお問い合わせください。
※家屋のうち、住宅を取り壊された場合、「住宅用地に対する課税標準の特例」の適用対象外となり、土地の税額が増額となる場合がございます。
<必要書類>
家屋滅失届(ワード形式 45キロバイト)
家屋滅失届(PDF形式 78キロバイト)
住宅改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれ一定要件を満たした家屋について、固定資産税が減額されることがあります。
ただし、バリアフリー改修と省エネ改修の重複適用以外の重複適用はありません。
住宅耐震改修に伴う減額措置
一定の耐震改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、申告により翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。
1要件
-
昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
-
令和8年3月31日までの改修工事であること。
-
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合していること。
-
耐震改修工事費が50万円を超えるものであること。
※耐震改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、平成29年4月1日以降の改修工事であること。
(地方税法附則第15条の9第1項)
2減額割合
改修家屋全体に係る固定資産税の2分の1が減額されます。
※認定長期優良住宅に該当する場合は、3分の2が減額されます。
3適用範囲
対象となる床面積は、1戸あたり120平方メートル相当分までです。
4減額期間
改修工事が完了した年の翌年の1回限り減額されます。
5申請方法
下記の必要書類を添付の上、工事完了後3か月以内に税務課へ申請してください。
<必要書類>
1.住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書
・「住宅耐震改修固定資産税減額申告書」
住宅耐震改修固定資産税減額申告書(ワード形式 49キロバイト)
住宅耐震改修固定資産税減額申告書(PDF形式 85キロバイト)
・「特定耐震基準適合住宅改修固定資産税減額申告書」(※長期優良住宅に該当する場合のみ)
特定耐震基準適合住宅改修認定長期優良住宅固定資産税減額申告書(ワード形式 50キロバイト)
特定耐震基準適合住宅改修認定長期優良住宅固定資産税減額申告書(PDF形式 154キロバイト)
2.現行の耐震基準に適合した工事であることの証明
※現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書の発行については、以下の機関に事前にお問い合わせください。
-
越前市木造住宅耐震改修促進事業の補助を受けて耐震改修工事を行った場合
越前市建築住宅課
-
上記事業の補助を受けずに耐震改修工事を行った場合
耐震改修の管理を行った建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人
3.工事明細書や写真等の関係書類
工事内容を示す書類は、建築士・登録性能評価機関等が発行する証明で代替可能です。
4.長期優良住宅認定通知書の写し(※長期優良住宅に該当する場合のみ)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
一定のバリアフリー改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、申告により翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。
1要件
-
建築された日から10年以上経過した住宅であること。
-
令和8年3月31日までの改修工事であること。
-
改修後の床面積が50平方メートル以上であること。人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。
-
次のいずれかの人が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)であること。
65歳以上の人、要介護認定又は要支援認定を受けている人、障がいのある人 -
次のようなバリアフリーのための工事であること。
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取付け、
床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化 -
バリアフリー改修部分の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること。
(地方税法附則第15条の9第4項または第5項)
2減額割合
改修家屋全体に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
3適用範囲
対象となる床面積は、1戸あたり100平方メートル相当分までです。
4減額期間
改修工事が完了した年の翌年の1回限り減額されます。
5申請方法
下記の必要書類を添付の上、工事完了後3か月以内に税務課へ申請してください。
<必要書類>
1.バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申請書
住宅バリアフリー改修固定資産税減額申告書(ワード形式 52キロバイト)
2. 工事明細書や写真等の関係書類
-
改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
工事内容を示す書類は、建築士・登録性能評価機関等が発行する証明で代替可能です。 -
改修工事の図面
- 改修工事箇所の施工前と後の写真
-
領収書の写し(工事が完了し、改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
-
本市要綱による住宅改修補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し(補助金額が確認できるもの)
-
上記居住要件の区分に応じた書類
65歳以上の人は、「住民票」の写し
要介護及び要支援認定を受けている人は、「介護保険の被保険者証」の写し
障がいのある人は、「身体障害者手帳」もしくは「療育手帳」の写し
住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額措置
一定の省エネ改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、申告により翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。
1要件
-
平成26年4月1日以前に存している住宅(賃貸住宅を除く)であること。
-
令和8年3月31日までの改修工事であること。
-
改修後の床面積が50平方メートル以上であること。 人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。
-
省エネ改修部分の工事で、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えること。
-
工事内容〈1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと〉
1.窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化)
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
※窓の改修工事は必須条件です。
※窓等の断熱改修工事費用が50万円を超える場合には、省エネに資する太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事費用と合わせて60万円を超える場合も対象となります。
※省エネ改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、 平成29年4月1日以降の改修工事であること。
(地方税法附則第15条の9第9項または第10項)
2減額割合
改修家屋全体に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
※認定長期優良住宅に該当する場合は、3分の2が減額されます。
3適用範囲
対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートル相当分までです。
4適用期間
改修工事が完了した年の翌年の1回限り減額されます。
5申請方法
下記の必要書類を添付の上、工事完了後3か月以内に税務課へ申請してください。
<必要書類>
1.省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
・「熱損失防止改修固定資産税減額申告書」
熱損失防止改修固定資産税減額申告書(ワード形式 51キロバイト)
熱損失防止改修固定資産税減額申告書(PDF形式 96キロバイト)
・「特定熱損失防止改修固定資産税減額申告書」(※長期優良住宅に該当する場合のみ)
特定熱損失防止改修認定長期優良住宅固定資産税減額申告書(ワード形式 51キロバイト)
特定熱損失防止改修認定長期優良住宅固定資産税減額申告書(PDF形式 170キロバイト)
2.工事明細書や写真等の関係書類
-
現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書等の関係書類
-
改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
-
改修工事の図面
-
改修工事箇所の施工前と後の写真
-
領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
3.長期優良住宅認定通知書の写し(※長期優良住宅に該当する場合のみ)
非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造等)の冷蔵倉庫の評価額見直し
平成24年度から非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造等)の冷蔵倉庫(保管温度が10度以下に保たれる倉庫)の評価額の計算方法が変更されました。それまで非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が10度以下に保たれる倉庫)」については、「一般の倉庫」と同じ取扱いとされていましたが、平成24年度からは「一般の倉庫」に比べて評価額が早く減少する補正率を適用して計算されることになりました。
越前市内に所有されている倉庫が以下の冷蔵倉庫に該当すると思われる人は、税務課資産税グループまでご連絡いただきますようお願いいたします。現地調査にお伺いし、該当するかどうかの確認をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。
[対象となる冷蔵倉庫]
- 非木造(鉄筋鉄骨コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造、コンクリートブロック造等)の倉庫用建物であること。
- 倉庫内は冷蔵設備によって常に10度以下に保たれていること。
- 建物全体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用されている部分がある場合、床面積の50パーセント以上が冷蔵倉庫)となっていること。倉庫内に単に冷蔵庫を設置しているような場合は、ご連絡は不要です。
《参考》平成21年総務省告示225号
地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の規定に基づき、昭和38年自治省告示158号(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続きを定める件)の一部を次のように改定し、平成24年度分固定資産税から適用する。別表第13-7-(2)中「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改める。
添付ファイル
- 家屋補充課税台帳所有者変更届(PDF形式 97キロバイト)
- 家屋滅失届(PDF形式 78キロバイト)
- 住宅耐震改修固定資産税減額申告書(PDF形式 85キロバイト)
- 特定耐震基準適合住宅改修認定長期優良住宅固定資産税減額申告書(PDF形式 154キロバイト)
- 住宅バリアフリー改修固定資産税減額申告書(PDF形式 92キロバイト)
- 熱損失防止改修固定資産税減額申告書(PDF形式 96キロバイト)
- 特定熱損失防止改修認定長期優良住宅固定資産税減額申告書(PDF形式 170キロバイト)
閲覧ソフト Acrobat Reader DC