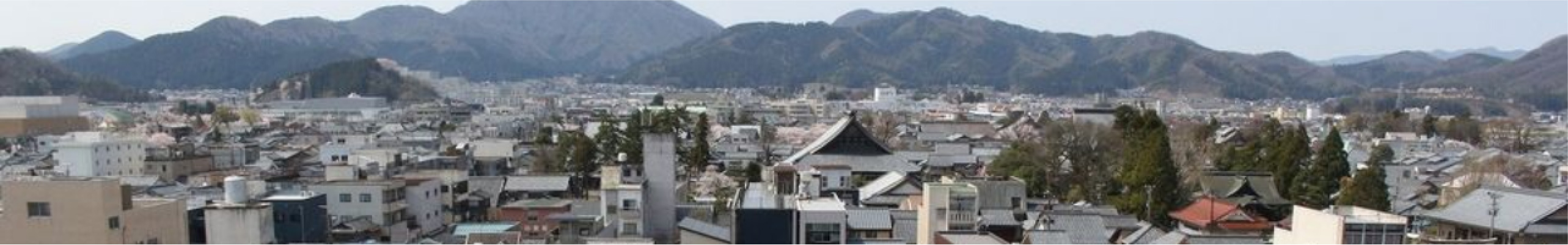最終更新日 2025年4月1日
広域避難場所に備蓄資機材を分散配備しました(防災危機管理課トピックス)
PAGE-ID:11755
広域避難場所に備蓄資機材を分散配備しました。令和7年3月
市では災害に備え、長期保存可能な食料や防災資機材の備蓄を行っています。
昨年の能登半島地震では、発災直後からの避難所環境、道路寸断による物資輸送などが課題となったことから、市内の広域避難場所(小中学校の体育館等)に毛布やマット、ブルーシート、発電機などの資機材を分散配備し、避難所開設当初から避難者に配慮した環境を提供できる体制を整えました。
今後も資機材の拡充し避難所環境の改善を図るとともに、資機材を活用した防災訓練を実施するなど、地域の防災力向上に努めてまいります。


越前市交通安全母の会総会が開催されました。令和7年3月8日
3月8日(土曜日)に越前市生涯学習センター今立分館で、山田賢一越前市長、齋藤祐司越前警察署長、近藤光広越前市議会副議長を来賓に迎え、越前市交通安全母の会総会が開催されました。
加藤のぶ子会長は「一人ひとりの声掛けで、明るい街づくりに貢献していきたい。」山田市長からは「市では自転車乗車時のヘルメット着用を推進している。母の会の皆様の地域の寄り添ったきめ細やかな活動が必要不可欠で、なお一層の協力をお願いしたい。」また、齋藤越前警察署長からは「昨年も越前署管内では5人の尊い命が失われた。一人でも悲しい思いをさせないために、母の会の皆様方の力を貸していただきたい。」と挨拶がありました。
総会開催前には、山田市長を講師に招いたタウンミーティングも開催され、本市の令和7年度の取組みなどについて会員は関心をもって聞き入っていました。
越前市交通安全母の会は、今年度も交通死亡事故0”ゼロ”を目標に、市や関連団体と連携して地域に寄り添ったきめ細かな啓発活動を続けてまいります。

JA越前たけふ様と災害時協力協定を締結、災害用資機材のご寄贈をいただきました。令和7年2月18日
越前たけふ農業協同組合様は地域に密着し、地域に根差した社会貢献活動に積極的に取り組まれています。
この度はその活動の一環として、能登半島地震を踏まえ避難所の環境改善を進める本市に、災害用資機材「簡易トイレセット」30組の寄附を、2月18日(火曜日)に土本俊三代表理事組合長から山田賢一越前市長に贈呈いただきました。
また、災害時に必要とする物資について優先的に提供いただけるよう「災害時に必要な物資の調達等に関する協定」を締結しました。
市では、地域企業・団体と連携しながら大規模災害に備えてまいります。
越前市交通安全推進協議会の総会を開催しました。令和7年2月12日
越前市交通安全推進協議会は2月12日(水曜日)に市生涯学習センターeホールで、大久保健一越前市議会議長、齋藤祐司越前警察署長、澤崎秀之越前市教育委員会教育長、山室悦久交通課長を来賓に迎え、関係団体や会員事業所から約50名の参加のもと総会を開催しました。
まず、長年にわたり本市の交通安全の推進にご貢献をいただいた功績を称えて、個人や団体に本協議会会長の山田賢一越前市長から表彰状を授与いたしました。また、職場ぐるみで交通安全運動を推進して10年を経過した事業所を優良事業所に認定し、従業員の交通マナーの向上と事故防止を目指す市内事業所を新たにモデル事業所に指定いたしました。
協議に入る前に、越前警察署山室交通課長から令和6年の交通情勢について説明いただき、続いて、令和6年度交通安全運動行事等実施結果及び令和7年度交通安全運動実施要綱(案)、実施計画(案)について賛成多数で承認いただきました。
令和6年の市内の交通死亡事故は5人と、令和5年に続き高止まりとなっています。本協議会では、このような死亡事故が無くなるよう、また、少しでも人身事故を減らしていけるよう、より一層、交通事故防止に努めてまいります。

表彰対象者等は以下のとおり(敬称略)
交通安全功労者表彰:髙原富子、谷孝光、畠中文子、山田久志、山田甚一
交通安全功労団体表彰:大信トラスト株式会社
交通安全優良事業所認定:株式会社高野組
交通安全モデル事業所指定:大和建設株式会社

令和7年度越前市交通安全運動実施要綱
【基本目標】
1 年間の「交通死亡事故0“ゼロ”」を目指す。
2 人身事故の減少を図る。
3 自転車用ヘルメットの着用を推進する。
【運動の重点と取組み】
重点1 こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
重点2 歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
重点3 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底
重点4 交通安全啓発・広報の強化
2月4日からの大雪にかかる罹災証明書の発行について
本市では市内で発生した災害により被害を受けた方に、罹災証明書及び被災証明書を発行しています。証明書が必要な方は、以下の内容をご確認いただき、申請をお願いします。
〇必要な書類
〇申請期限
〇申請書の提出先
・窓口の場合:越前市役所3階 防災危機管理課 窓口まで提出してください。
・郵送の場合:下記の住所に送付してください。
〒915-8530 越前市府中一丁目13-7 越前市防災危機管理課宛て
小さないのちを守るために。幼児交通安全リーダー研修会を開催しました。令和7年2月3日
本研修会は、昨年から越前市交通安全推進協議会と越前警察署が共同開催しており、今回は越前警察署交通課署員を講師として招き、「幼児の交通事故の傾向やその対策、チャイルドシートの正しい着用について」と題して講話しました。
同署の宮田交通課係長は、幼児の特性について触れ、急な飛び出しや視野の狭さなど大人が注意すべき点のほか、繰り返し教えることの重要性や紙芝居や腹話術といった視聴覚に訴える教育方法の有効性等について説明されました。
また、質疑応答の時間には、日頃から幼児と接する幼稚園教諭や保護者ならではの質問が多く寄せられ、非常に有意義な研修会となりました。
市では、今後もこのような研修会を定期的に開催し、地域全体で幼児の交通安全教育に取り組んでまいります。

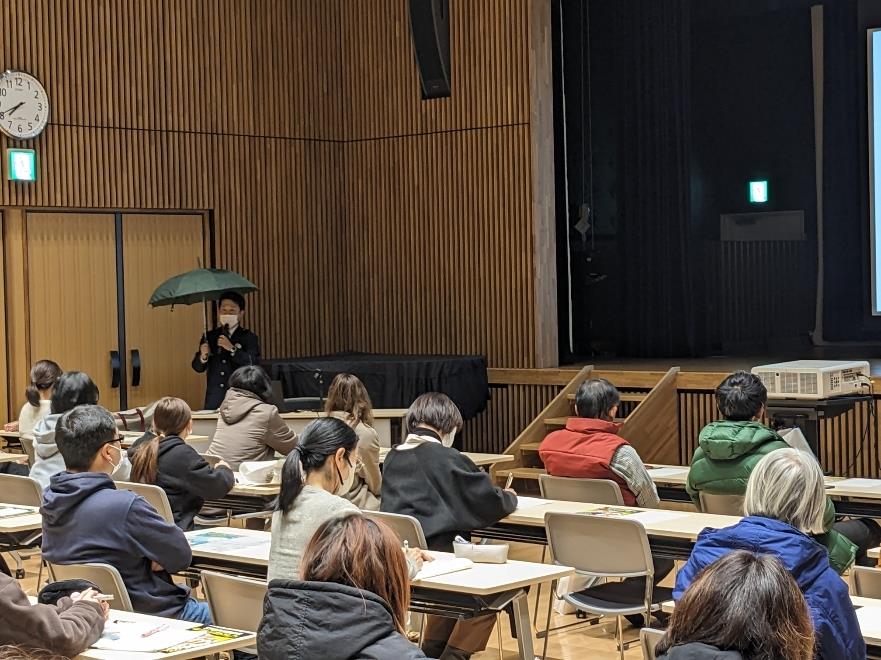
原子力施設の視察を行いました。令和7年1月17日
1月17日(金曜日)に越前市災害対策本部員13名が、関西電力株式会社美浜原子力発電所を視察しました。
美浜発電所PRセンターでは、VRゴーグルによる発電所施設内の見学を行い、原子力発電の仕組みや数々の災害への対策についての説明を受け、安全に対する取組みについて学びました。
発電所敷地内では、施設等の設置や補強工事に関する説明、また、緊急時対策所の見学を行い、万が一の事態が発生した場合にも万全の対策が取られていることを確認しました。
本市は、日本原子力発電敦賀発電所や関西電力美浜発電所など敦賀半島の原子力発電所から30キロ圏内に位置していることから、電力事業者と情報連絡体制を密にし市民の安全対策に努めてまいります。



今年1年の交通安全を祈願しました 。令和7年1月9日
今年1年の交通安全を願い、越前交通安全協会は1月9日(木曜日)に総社大神宮拝殿で、山田賢一越前市長、齋藤祐司越前警察署長など関係団体から約30人が参列のもと、交通安全祈願祭を開催しました。
同協会片岡建和会長は、昨年発生した交通死亡事故に触れ「県内の死者数は目標の25人以下を達成し、管内においても前年から1人減少したが、依然として死亡事故が絶えない。北陸新幹線の開業によって人の流れが増える中、関係団体と協力して死亡事故ゼロを目指したい」と挨拶の中で決意を述べられました。
市では、「安全・安心なまちづくり」の実現のため、 越前交通安全協会をはじめ関係団体の皆様と日頃からの連携した交通安全推進活動が実を結ぶよう一層取り組んでまいります。

年末の交通安全県民運動早朝一斉街頭指導に総勢150名が参加。令和6年12月11日
12月11日(水曜日)から20日(金曜日)までは年末の交通安全県民運動期間です。初日の11日は午前7時30分から1時間、市内の主要交差点で早朝一斉街頭指導を実施しました。
街頭指導には、市交通安全推進協議会の会員事業所、越前交通安全協会、市交通安全母の会など各種団体をはじめ、越前警察署員や市交通指導員ら約150名が参加し、登校中の学生や通勤中のドライバーに対し、交通事故防止を呼びかけました。
また、山田賢一越前市長や大久保健一市議会議長、齋藤祐司越前警察署長、片岡建和交通安全協会長らが各交差点を巡回し、早朝から街頭指導にあたった皆さんを激励しました。

 【運動の重点と取組み】
【運動の重点と取組み】
1 高齢者の交通事故防止(北陸三県統一)
2 夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶
3 雪寒期の交通事故防止
過去5年間の県内発生事故統計データによると、12月は月別の死亡重傷事故件数が最多で、歩行中の犠牲者も最多となっています。
ドライバーは…
・横断歩道は歩行者優先、渡ろうとする人がいるときは、必ず一時停止しましょう。
・降雪などで悪天候の日も多くなります。悪天候や夜間は、普段よりスピードを落として安全運転に心がけましょう。
・日没も早まることから、早めのライト点灯や夜間のハイビームを心がけましょう。
歩行者は…
・道路を横断するとき、必ず、左右の安全確認をしましょう。
・横断歩道を渡る時は、手を上げる、ドライバーに顔を向けるなどして意思表示をしましょう。
一人ひとりが交通ルールの遵守や正しい交通マナーの向上に努め、交通事故防止の徹底を図りましょう。
市防犯隊が年末警戒パトロールを実施しています。令和6年12月6日
今年も残すところ3週間となりました。年末年始はスリやひったくり、空き巣や強盗等の犯罪が増加する傾向にあります。また、最近では、全国的に闇バイトによる強盗事件等が発生しています。
越前地区防犯隊連合会では住民が穏やかに年を越せるよう、11月18日から越前地区安全安心まちづくり推進パトロールを実施しています。12月6日(金曜日)午後6時10分から越前地区安全安心まちづくり推進パトロール督励式が開催され、山田賢一越前市長と齋藤祐司越前警察署長から、防犯パトロール活動を行う越前市防犯隊員と越前警察署員に激励のご挨拶がありました。
その後、パトロールカーと青色回転灯装備車両15台が一斉に市内の防犯パトロールに出動しました。
皆さんも事件や事故に巻き込まれないように、心に「すき」を作らないよう注意しましょう。



令和6年度坂口地区防災訓練(市総合防災訓練)が開催されました。 令和6年11月23日








「かぶろっさ!ヘルメット」菊花マラソンで着用を啓発。令和6年11月3日

 令和6年の県内交通死亡事故(11月3日現在)20件のうち5件が自転車事故で、亡くなった自転車乗用者すべてがヘルメット非着用でした。自転車乗車中の死亡事故について、ヘルメット着用時と比較して非着用時は致死率が約2.4倍になるといわれています(令和5年版交通安全白書)。
令和6年の県内交通死亡事故(11月3日現在)20件のうち5件が自転車事故で、亡くなった自転車乗用者すべてがヘルメット非着用でした。自転車乗車中の死亡事故について、ヘルメット着用時と比較して非着用時は致死率が約2.4倍になるといわれています(令和5年版交通安全白書)。災害時相互応援協定を締結する碧南市が本市を訪問されました。令和6年10月30日


県原子力総合防災訓練で小浜市から避難者受入れ訓練を実施。令和6年10月26日
福井県嶺南を震源とする地震により大飯発電所が全面緊急事態になったという想定で県原子力総合防災訓練が10月25日、26日に開催され、本市では26日に同発電所のUPZ圏内にある小浜市民の受入訓練を南越中学校で実施しました。
拠点避難所となった武生東運動公園で通行証の確認のあと、小浜市民72名を乗せたバス4台が正午前に南越中学校に到着しました。また今回は福井工業大学の学生約20名も本市への避難訓練に参加されました。避難所として設営した体育館では、小浜市職員や本市防災担当職員総勢15名が受付や会場の整理、案内などの訓練を行いました。
会場には、杉本和範小浜市長、山田賢一越前市長をはじめ、杉本達治福井県知事が訓練の状況を視察に訪れ、避難所の様子や展示ブースなどを見学されました。本市の山田市長は「今回は避難者を受け入れる側の立場として貴重な経験を得ることができた。この知見を蓄えて本市の広域避難の参考にしたい。」と挨拶いたしました。また杉本小浜市長からは本市の受入れ体制に感謝の言葉をいただきました。
万が一の際には、一人ひとりの「自助」と避難住民の「共助」、そして越前市と小浜市が共に助け合っていくことが必要となります。本市も敦賀・美浜地域で原子力災害が発生した時は避難者になります。今回の訓練では、避難者を受入れる側としての参加でしたが、両方の立場での訓練経験を生かして災害対応に努めます。



吉野地区自主防災組織本部スタッフ研修会を実施しました。令和6年10月12日、24日
吉野地区では、災害発災時に各町内での被害情報や地域住民の安否を取りまとめ、市災害対策本部への伝達など初期対応の共通認識を図るため、10月12日(土曜日)に吉野公民館で自主防災組織本部スタッフ(地区拠点基地運営) 研修会(災害図上訓練・DIG)を実施しました。また、24日(木曜日)には訓練対応の振り返り研修を行いました。
図上訓練では、電話で聞き取った被害状況を付箋に書いて地図に貼り付け地区全体の状況の共有し、地区を担当する職員から市災害対策本部への報告を行うまでの訓練を実施しました。振り返り研修では、被害状況と人命に係る情報が仕分けできていなかったことから、報告を整理するルール化が必要などの意見を交わしました。また、災害種別による町内集会場の開設について、住民への周知徹底を行うことなどを確認しました。
同地区では、昨年から地区防災計画作成に向けた組織体制の強化を、自治振興会役員や区長会、地区在住の防災士が一体となって取り組んでいます。令和7年度には全町内の住民参加による避難訓練の実施を予定しています。
地区の特性を知る住民主体の助け合いの仕組みづくりや防災意識向上に対し、市では引き続き支援を行ってまいります。

サンドーム福井で防災ふれあいプラザが開催されました。令和6年10月23日
10月23日(水曜日)午前9時からサンドーム福井イベントホールで防災ふれあいプラザが開催されました。越前市幼年消防クラブと南越消防組合中消防署・東消防署の主催で、市内29の認定こども園、幼稚園から約650人の園児たちが参加しました。
会場には救急車や消防車、はしご車などの展示のほか、消防体験コーナーが数多く設置され、煙体験や放水体験、起震車搭乗体験、心臓マッサージ体験など、園児たちは楽しみながら防火・防災を学びました。
今年は、自衛隊福井地方協力本部の協力により自衛隊車両も展示され、地震や大雨などの大規模災害時の活動が紹介されていました。



OSK日本歌劇団スターが一日警察署長として交通安全を呼びかけました 。令和6年10月14日
たけふ菊人形「OSK日本歌劇団たけふレビューinたけふ菊人形」に出演している天輝(あまき)レオさんが、10月14日(祝)一日警察署長として交通安全啓発活動を行いました。
公演終了後、ステージ上で齋藤祐司越前警察署長から1日警察署長を委嘱され、その後、菊人形正面ゲート前のエントランス広場に移動し、おおくのファンや菊人形来場者などに道路横断時の安全確認などを呼びかけました。

 菊人形正面ゲート前の横断歩道は福井県警察の重点横断歩道として、県内32箇所(市内3箇所)の一つで、歩行者妨害違反の取り締まり強化箇所となっています。
菊人形正面ゲート前の横断歩道は福井県警察の重点横断歩道として、県内32箇所(市内3箇所)の一つで、歩行者妨害違反の取り締まり強化箇所となっています。
啓発活動には同歌劇団の唯城(ゆしろ)ありすさんも参加し、越前署員とともに横断旗を手に歩行者の安全を見守り、市交通指導員と一緒にチラシや反射材を配布しました。
 越前市では7月以降4件の交通死亡事故が発生しており、そのうち3件が横断歩道上での事故です。
越前市では7月以降4件の交通死亡事故が発生しており、そのうち3件が横断歩道上での事故です。
横断歩道は歩行者優先ですが、渡るときは手をあげる、ドライバーに顔を向けるなど横断意思表示を行い、しっかり安全確認をして渡りましょう。
ドライバーは、横断歩道を横断しようとする歩行者がいるときは、必ず、一時停止しましょう。横断するときのルールを学ぼう!交通安全ふれあい教室を開催しました。令和6年10月8日




越前市交通指導員会が菊人形会場で交通安全茶屋を実施しました。令和6年10月5日
本市では7月以降4件の交通死亡事故が発生したことをうけて、交通死亡事故防止のため、市交通安全母の会、市交通指導員会など関係団体と協力して啓発活動等の取組みを強化しています。
10月5日(土曜日)には午前9時から菊人形開場に合わせ、市交通指導員会が武生中央公園で通安全茶屋を実施しました。酒田家男会長ほか指導員17名がたけふ菊人形の来場者に、反射材付きエコバックや啓発チラシ、お茶を配布し交通事故防止を呼びかけました。

認定こども園岡本の園児と一緒に安全運転を呼びかけ!交通安全母の会が安全茶屋を実施しました。令和6年10月4日
10月4日(金曜日)午前10時頃から、認定こども園岡本の年長児12名のほか市交通安全母の会会員9名が越前警察署や地域交通安全活動推進委員に協力いただき、総勢35名で越前市交通安全母の会交通安全茶屋が実施されました。
大粒の雨が降り注ぐなか、あいぱーく今立前の県道を走る車両を駐車場内に誘導して、交通安全のメッセージを書いた啓発グッズやお茶、反射材など150セットを配りドライバーに安全運転を呼びかけました。
園児の「あんぜんうんてんをしてください」「雨の日のうんてん、気をつけてください」などの明るく元気な呼びかけに、ドライバーも笑顔で応えてくれました。

 本市では7月以降4件の交通死亡事故が発生しています。市交通安全母の会や市交通指導員会など関係団体と協力して、啓発活動に取組んでまいります。
本市では7月以降4件の交通死亡事故が発生しています。市交通安全母の会や市交通指導員会など関係団体と協力して、啓発活動に取組んでまいります。
令和6年度上半期トピックスはこちら
令和5年度下半期トピックスはこちら
令和5年度上半期トピックスはこちら
令和4年度下半期(1~3月)トピックスはこちら
令和4年度下半期(10~12月)トピックスはこちら
令和4年度上半期トピックスはこちら
令和3年度下半期トピックスはこちら
令和3年度上半期トピックスはこちら