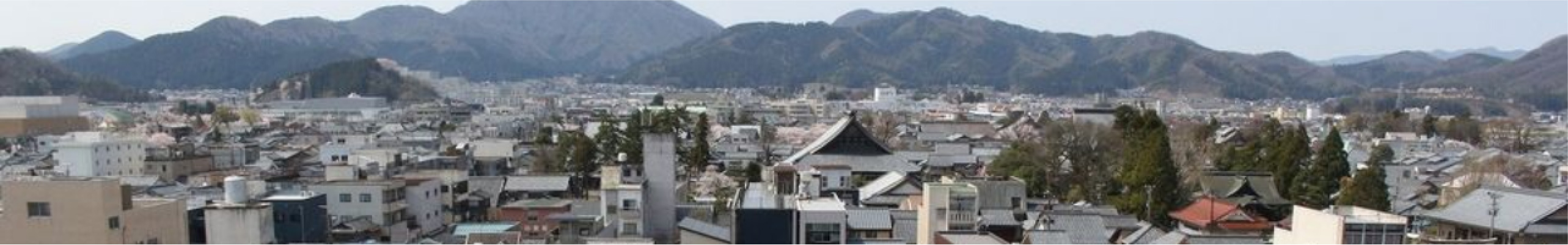信州安曇野松川村より視察3月7日
松川村は、令和7年4月から「こども家庭センター」を開設するとのことで、越前市が今年度開設した「こども家庭センター」(市民プラザたけふ4階)と「乳幼児教育・保育支援センター」の取組を、教育長や教育委員など5名の方が視察に来られました。
初めに、乳幼児教育・保育支援センターのある「にじいろこども園」の施設をご覧になりながら、医療的ケア児の受け入れや教育・保育環境の整備などについて意見交換をしました。
センターでは、越前市と松川村それぞれの「切れめない支援」や「教育・保育ニーズへの対応」などの取組や課題について意見交換をしました。
越前市の特産物についても話題に上がりました。松川村には「安曇野ちひろ公園」があり、いわさきちひろさんの作品が展示してある美術館があるそうです。いわさきちひろさんの生家がある越前市とのつながりを感じました。
かにまるフェスタに行ってきました。2月7日
武生西小学校で開催された「かにまるフェスタ」に、にじいろこども園の4・5歳児と一緒に行ってきました。6年生児童が主催するSDGsをテーマにしたイベントです。児童企画のパンやクレープ、廃品を活用したおもちゃやアクセサリーなどが販売されていたり、SDGsを伝えるクイズや動画、製作ブースがつくられていたりしました。
また、武生西小学校出身で武生高等学校2年生の生徒が一人で 「金継ぎ」のブースを出していました。伝統工芸に興味をもち、現在は「金継ぎ」の魅力を後世に伝える活動をしているそうです。小学校のころからいろいろな活動に積極的に参加していたとのことでした。
「かにまるフェスタ」を開催した6年生の皆さん、伝統工芸を後世に伝える活動をしている生徒さん、どちらもいきいきと活動されていて参加した私たちもたくさんの刺激をもらいました。ありがとうございました!
先進地視察の報告会をしました。12月18日
このみらいで毎月行っている定例会で舞鶴市視察の報告会をしました。にじいろこども園からはクラス担任の方も参加してくださいました。
舞鶴市乳幼児教育センターの概要をお伝えした後、職員が公開保育を行う園にどのように関わっていったか、幼小連携活動で園や学校をどのように支援していったかなどについて報告させていただきました。参加の皆さんから質問やご感想をいただきました。私たち「このみらい」も園や学校としっかりつながってこれからも取り組んでいきたいと思います。
先進地視察に行きました!11月29日
舞鶴市乳幼児教育センター(2019年4月に開設) へ行ってきました。職員の方にセンターの取組や実績について教えていただきました。今年4月に開設した私たちにはすべてが参考にさせていただきたいことばかりで、身の引き締まる思いで帰ってきました。公開保育をされたばかりの「タンポポこども園」も見学させていただきました。園内には乳幼児教育センターと一緒に取り組んだ足跡が随所に見られました。
(福)和楽園で研修会をしました!
センター(このみらい)の幼小接続コーディネーターが『幼児期の育ちを学童期へ』と題して研修会を開き、(福)和楽園の5園から4・5歳児の担任保育士が、南 保育園に集まりました。
はじめに動画「1年生の一日」を視聴。元気にあいさつをしたり友だちの発表をよく聞いて返事や拍手をしたりする児童の姿に感心していました。と同時に、考えたことを言葉にして発表したり文章を読んで考えたりする場面では、自園児がそこまでできるようになるかなと不安を感じるという声も聞かれました。
次に入学説明会資料から「生活」「登下校」「学習」について園児の様子を思い浮かべながら話し合いました。何より園と小学校が連携することが大事で、入学説明会資料をもらうこと(できれば参加)、小学校へちょこっと訪問をして気軽に話せる間柄になること、子どもたちが小学校に行く回数を一度でも多くつくることをお願いしました。
地区文化祭に子どもたちが参加!
文化の秋!各地区で文化祭が開かれています。
9月28日(土曜日)29日(日曜日)に西地区の「西地区ふれあいフェスタ」と「西地区文化祭」が行われました。会場は、武生西公民館や児童センター、武生西小学校、にじいろこども園の交流スペースなどでした。地域の小中学生のダンスやたくさんの催しコーナーがあり、お年寄りから小さな子どもまでいろいろな世代や国籍の方が集まって大変にぎわいました。文化祭では、にじいろこども園5歳児がカラーガードの演技を披露しました。たくさんの笑顔と拍手をもらい、子どもたちも大満足。地域の中で大切に育つ子の姿が垣間見れました。他地区においても同様に子どもたちと地域の交流が進められています。地域の皆さんありがとうございます。



定例会を開きました
センター(このみらい)では仁愛大学石川昭義教授をアドバイザーに毎月定例会を開催しています。今回は動画「1年生の一日」の視聴から始まりました。1年生の伸び伸びした様子から担任の先生が園とのつながりを大事にして対応されているのを感じることができました。参加した保育士、園長、小学校教諭を交え、園の遊びから学校の教科型学習へどのように繋いでいくとよいか話し合いました。
センター(このみらい)を利用できます!
乳幼児教育・保育支援センター(このみらい)は研修の場所として自由に使っていただくことができます。今日は公立園の1歳児年齢別研修が行われ、センターの職員も参加させていただきました。


保育士の皆さんが日ごろの悩みや取組について話し合っています。


手作りおもちゃや環境づくりについて情報共有していました。手遊びや体操も練習していました。会議やちょっとした打ち合わせなどいろいろな場面でセンターを利用してください。
山田市長がセンターにお見えになりました!
6月4日、山田市長がにじいろこども園を訪問されました。センターにも足を運んでくださいました。
市長は、にじいろこども園の子ども達や保護者の方と気さくにお話をしていました。
1年生国語の授業(5月28日)
小学校1年生国語「わけをはなそう~もっとなかよしだいさくせん! ~」の授業を参観しました。めあては「こたえ」と「そのわけ」をつたえあおうです。

ICT機器を使って「こたえ」と「そのわけ」の話し方を分かりやすく示しています。友だちに聞きたいことや友だちのことで知りたいことをみんなで出し合った後、伝え合いの活動をしました。

上の写真は、最後の振り返りで先生から大きな花丸を受け取っているところです。上手に伝え合い、もっとなかよしだいさくせん!は大成功。手をいっぱいに伸ばして受け取った大きな花丸は、ポケットにぎゅっとしまいました。きっとおうちまで大事に持って帰ったことでしょう。

黒板の端に「文字を書く4つの部屋」の小黒板と「えんぴつをただしくもとうの歌」の歌詞カードが貼ってあります。今日の授業の前に子どもたちが「えんぴつをただしくもとうの歌」を 楽しそうに歌っていました。
当センターは、福井県幼児教育支援センタ―や他自治体の幼児教育アドバイザー、大学・専門機関等と積極的に繋がっていきます。
福井市麻生津小学校1年生見学
麻生津小学校の斎藤校長は、県幼児教育支援センター設立初期に指導主事として赴任され、当市の保育の質向上のため、研修や公立園公開保育のアドバイザーとして平成26年ごろから指導を仰いでいた方です。
<校長室にて>

他市の幼小接続推進の取り組み視察
~大野市幼小接続推進協議会の様子~5歳児~小1年生の架け橋期の子どもの学びの特徴と、子どもにかかわる保育者や教諭の役割についての講義後、市内の園長と小学校校長で、幼小接続の意義や具体的取り組みについて意見交換を行ました。

会議終了後、大野市幼児教育アドバイザー3名、県幼児教育支援センター、市教育総務課、こども支援課の方と意見交換の時間をいただきました。子どものゆたかな学びのため、幼小それぞれの役割や専門性を伝え合うことを積み上げていることの成果を実感されているとのこと、素晴らしいと感じました。
外国籍児支援研究グループの先生来園
吉永安里教授(國學院大學) 、岡本拡子教授(高崎健康福祉大学)、佐々木由美子教授(足利短期大学)が、にじいろこども園と乳幼児教育・保育支援センターを視察にいらっしゃいました。外国籍児や医療的ケア児などを含めた子ども達の生活と遊びの様子や、子どもにかかわる様々な立場の職員について、園・センター職員と意見交換を行いました。



市内各園をまわり始めました!
各園の先生方のご意見をお聞きしながら、取り組んでいきます。
どうぞよろしくお願いします。

今後、園の子ども達の遊びや学びの様子も紹介していく予定です。

☘今回訪問した園の5歳児の当番活動の一コマ☘
飼育しているうさぎちゃんにエサやりと水やりのお仕事中です。