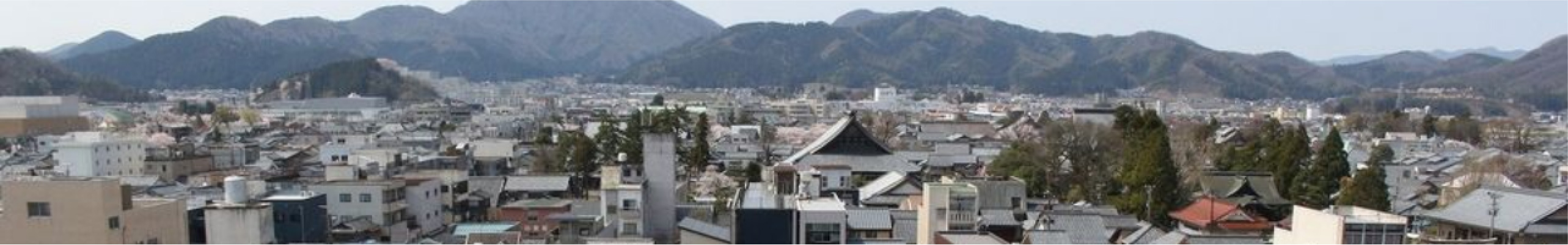最終更新日 2026年2月3日
まつりと伝統行事
PAGE-ID:2901
まつりと伝統行事
越前市では一年を通して様々なまつりや伝統行事が行われています。
越前万歳初舞

日本三大古典万歳のひとつで国の無形民俗文化財に指定されている。
新年を祝って、繁栄を願うおめでたい歌詞を歌い舞う郷土芸能。
毎年1月1日に味真野神社で初舞が行われる。
惣田十七日講(ごぼう講)

毎年2月17日に越前市の国中町にて行われる「惣田正月十七日講」。
山盛りのごぼうを食べることから別名「ごぼう講」と言われている。
約300年続いており、その年の宿主となった家で行われる。
昔、貢租の重圧をはねのけるために村人同士の団結強化ではじめられたといわれている。
蓬莱祀(おらいし)

約1,500年前に越前市ゆかりの継体天皇の即位を祝い、三里山(蓬莱山)を模して山車を飾り、
五穀豊穣と国家安全を祈ったのが始まりとされる伝統行事。
毎年、2月11日に式典と山車の引き回しが行われる。
詳しくは蓬莱祀保存会のホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
あじまの万葉まつり

毎年5月3日から4日にかけて万葉の里味真野苑を中心に行われる祭り。
万葉中学生をはじめ地元住民が古代衣装に身を包み、雅楽の優雅な音色に合わせて厳かに練り歩く。
万葉の里では、地場産品の販売や万葉大茶会、バンド演奏、和太鼓、万葉相聞歌朗唱などが多彩に繰り広げられる。
詳しくは味真野観光協会のページをご覧ください。
神と紙のまつり

約1,500年前に紙漉きの技術を伝えたとされている紙祖神 川上御前を祀る岡太神社・大瀧神社の春例祭。
毎年5月3日から5日の3日間開催され、和紙の里通りでは越前和紙の特売市が開かれるほか、
様々な屋台、特産品のバザー等が軒を並べる。
詳しくは福井県和紙工業協同組合のホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
みたま祭り

毎年7月15日に金剛院で行われる祭り。
境内に6,000本のろうそくが置かれる様子はとても幻想的。
その他、七夕飾りのお焚きあげや「地獄図絵」の展示が行われる。
越前市サマーフェスティバル

毎年8月中旬頃に開催される。
最終日の花火大会は日野川河川敷で行われ、爆音が村国山に反響するため迫力満点だ。
詳しくは越前市サマーフェスティバルのホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
武生国際音楽祭

毎年9月上旬頃に一週間ほど開催される音楽祭で、世界で活躍する音楽家の演奏を聴くことができる。
メイン会場の越前市文化センターだけでなく、寺社仏閣等でも演奏会が開かれ、まちなかに音楽が響きわたる。
詳しくは武生国際音楽祭のホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
総社めおとみこし

毎年9月中旬に開催される総社大神宮例祭のメインイベント。
みこしが始まった明治5年当初は男衆が担いでいたが、まちおこしの一環として平成5年に女性が担ぐ「姫みこし」を実施し、
以降「男みこし・姫みこし」として毎年行われてきた。
現在は「めおとみこし」に形を変え引き継がれている。
鬼ヶ嶽火祭り(おにがたけひまつり)

毎年8月15日夕方に松明をかかげた行列が大虫神社を出発し鬼ヶ嶽を登る神事。
鬼ヶ嶽は「丹生ヶ嶽」と呼ばれていたが、山腹に白い鬼女が住みついて村人を襲っていたのを
村の若者たちが退治し、鬼ヶ嶽と呼ばれるようになったといわれている。
獅子返し(ししがえし)

9月下旬から10月上旬にかけて、村の若衆が獅子頭を持ち村役や新築の家に訪れ勇壮な獅子舞を舞う祭り。
南中山地区の野岡町・山室町・東庄境町・赤坂町・国中町・中津山町、
服間地区の朽飯町・室谷町、岡本地区の南坂下町の村祭りで開催される。
たけふ菊人形
毎年10月上旬から11月上旬に武生中央公園で開催される日本最大級の菊人形展。
会場内には約2万株もの菊花が咲き誇り、甘い菊の香りが漂う。
詳しくはたけふ菊人形のホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)