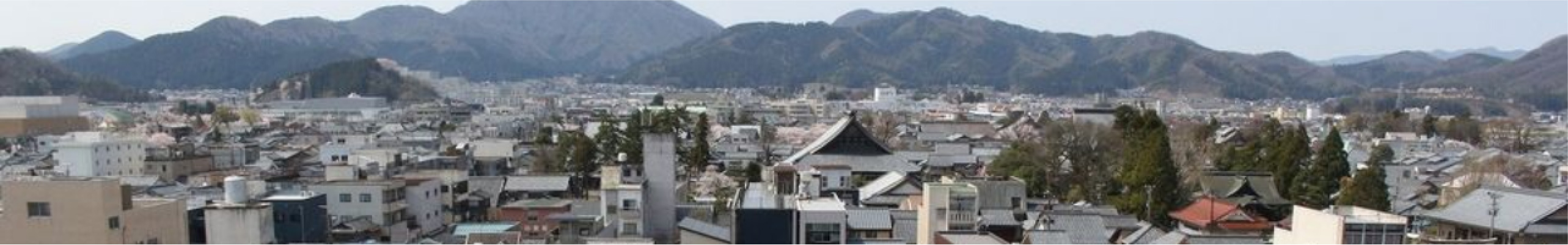最終更新日 2023年11月27日
越前市の歴史年表
PAGE-ID:1669
越前市の歴史
| 時代 | 年号 | 西暦 | 越 前 市 の で き ご と | |||||
| 縄文 | 紀元前 | 11000年 | このころ、尖頭器を使用する(領家遺跡) | |||||
| 3000年 | このころ、石斧・石鏃や縄文土器を使った生活(東樫尾遺跡など) | |||||||
| 人々は採集や狩をし、武生盆地の丘やふもとで生活 | ||||||||
| 弥生 | 紀元前 | 300年 | このころ、稲作や金属器の使用が始まり、平地に水田が開かれ、「むら」もできる | |||||
| 古墳 | 400年 | このころ、松明山の方墳に「家屋人物獣文鏡」や「首飾り」が副葬される | ||||||
| このころ、船山・愛宕山などに前方後円墳が造られる | ||||||||
| 男大迹王、樟葉宮で即位し継体天皇となる(『日本書紀』) | ||||||||
| このころ、機織の技術が服部谷へ、和紙の製法が大滝に伝わったとされる | ||||||||
| 600年 | このころ、茶臼山・大屋・宮谷などに群集墳が造られる | |||||||
| このころ、王子保地区で須恵器・瓦・塼仏(せんぶつ)などが生産される | ||||||||
| 大和 | 大化元 | 645年 | ||||||
| 658年 | 越前守阿部比羅夫、蝦夷を征討する | |||||||
| このころ、深草・野々宮・大虫の各寺が建立される | ||||||||
| 692年 | このころ、越の国が越前(加賀・能登を含む)・越中・越後の三国に分割される | |||||||
| 大宝元 | 701年 | |||||||
| 和銅元 | 708年 | 高志村君、越前守として太介不(たけふ)に「国府」を置く | ||||||
| 奈良 | 3 | 710年 | ||||||
| 7 | 714年 | 中山里から都へ白米や赤米が送られた(長屋王邸出土木簡) | ||||||
| 養老 2 | 718年 | 越前国を分割して能登国を置く | ||||||
| 天平 2 | 730年 | 正倉院に残る「大税帳」の用紙は越前で漉かれた | ||||||
| 5 | 733年 | 丹生郡領は佐味浪麻呂であった | ||||||
| 11 | 739年 | このころ、中臣宅守が味真野に流される | ||||||
| 勝宝元 | 749年 | 大伴池主、越前の掾として赴任する | ||||||
| このころ、越前にも国分寺・国分尼寺が建立される | ||||||||
| 宝字 8 | 764年 | 越前守恵美辛加知が恵美押勝の乱で殺される | ||||||
| このころ、室谷に古代寺院が建立される | ||||||||
| 平安 | 弘仁14 | 823年 | 越前国から「加賀国」が分かれる、丹生郡から「今立郡」が分かれる | |||||
| 承和 5 | 839年 | 味真公御助麻呂、本籍を左京五条二坊へ移す | ||||||
| 14 | 847年 | 丹生郡の春日部雄継、外従五位下を授かる | ||||||
| 延長 5 | 927年 | 「延喜式神名帳」に越前国大虫神社、国中神社、岡本神社の名が記される | ||||||
| 長徳 2 | 996年 | 紫式部、父越前国守藤原為時とともにたけふに来る | ||||||
| 寿永 2 | 1183年 | 木曽義仲、越前国府に陣を構える | ||||||
| 鎌倉 | 文永 5 | 1268年 | 螢山、越前多禰(たね:越前市)に生まれる | |||||
| 弘安元 | 1278年 | 五箇で間似合紙が発明される | ||||||
| 正応 3 | 1290年 | 他阿真教、総社に参詣し、越前で布教する | ||||||
| 室町 | 建武元 | 1334年 | このころ、京の刀鍛冶千代鶴国安、府中で越前鎌の技術を伝えたといわれる | |||||
| 3 | 1336年 | 斯波高経、越前守護となる | ||||||
| 暦応元 | 1338年 | 斯波高経、日野川で新田義貞軍と戦う | ||||||
| 4 | 1341年 | 大滝城、北朝軍に攻められ落城する | ||||||
| 5 | 1342年 | 斯波高経、道西掃部に御教用紙(越前奉書)を漉くよう命じる | ||||||
| 貞和元 | 1345年 | 別印山日円寺が越前の安国寺に指定される | ||||||
| 5 | 1366年 | 良如、正覚寺を開く | ||||||
| 正平23 | 1368年 | 通幻寂霊、竜泉寺を開く | ||||||
| 文明 3 | 1471年 | 将軍義政、朝倉孝景に越前守護の御内書を与える | ||||||
| 6 | 1474年 | 斯波政綿、大滝寺に神領を寄進する | ||||||
| 12 | 1480年 | 大乗院寺社雑事記の地図に府中守護所が記される | ||||||
| 13 | 1481年 | 朝倉孝景、大滝寺の寺領を安堵する | ||||||
| 長享 2 | 1488年 | 真盛、引接寺を開く | ||||||
| 明応 5 | 1496年 | このころ、朝倉氏家臣、青木・印牧両氏が府中奉行人となる | ||||||
| 天文12 | 1543年 | 公家清原枝賢、府中祭を見物する | ||||||
| 22 | 1553年 | 一乗谷奉行人小泉左衛門が粟生寺へ田畑を寄進する | ||||||
| 天正元 | 1573年 | 織田信長、朝倉氏討伐のため府中に入る 前波長俊、大滝寺の寺領安堵する | ||||||
| 安土桃山 | 天正 2 | 1574年 | 府中城主富田長繁、大滝寺と門前へ禁制を出す 長繁、越前一向一揆に討たれる | |||||
| 3 | 1575年 | 信長、一揆討伐のため再び府中に入る 滝川一益、大滝寺などを焼き討つ 府中10万石を不破光治・前田利家・佐々成政(府中三人衆)に与える 信長、大滝掃部に奉書紙販売の特権を与える 府中三人衆、五箇村紙座の特権を許す 佐々成政、粟田部付近で検地を行う | ||||||
| 4 | 1576年 | 一揆起り、前田利家これを平定する(小丸城跡出土瓦) | ||||||
| 7 | 1579年 | 佐々成政、成願寺へ禁制を出す | ||||||
| 9 | 1581年 | 佐々成政、大滝掃部に奉書紙の特権を与える | ||||||
| 11 | 1583年 | 豊臣秀吉、柴田勝家を追って府中に入る 秀吉の御陣屋普請に粟田部のかち村大工が当たる 秀吉、岩本村と新堂永林寺へ禁制を出す 丹羽長秀、大滝寺へ禁制を出し、大滝掃部に奉書紙職を安堵する | ||||||
| 13 | 1585年 | 木村隼人佐、若狭より府中に入る | ||||||
| 文禄元 | 1592年 | 青木秀以、府中金剛院に拠る | ||||||
| 4 | 1595年 | このころ、秀吉が大滝掃部に桐の印を許し、奉書紙職の特権を与える | ||||||
| 慶長元 | 1596年 | このころ、青木一矩が夫役受取状を大滝村へ渡す このころ、善照、清水頭に毫摂寺を移す | ||||||
| 3 | 1598年 | 長束正家らによる越前の検地完了する | ||||||
| 4 | 1599年 | 堀尾可晴、府中城主となる 可晴、大滝掃部の特権を安堵する | ||||||
| 5 | 1600年 | 結城秀康、将軍より越前一国68万石を拝領する | ||||||
| 6 | 1601年 | 本多富正、秀康より3万7千余石を拝領し府中城主となる 秀康、三田村掃部を奉書紙職に任命する | ||||||
| 江戸 | 8 | 1603年 | ||||||
| 17 | 1612年 | 福井藩で久世騒動が起きる | ||||||
| 元和元 | 1615年 | 大阪夏の陣で本多富正大阪城一番乗りの功名をたてる | ||||||
| 9 | 1623年 | 富正、加増されて4万5千石の領主となる | ||||||
| 寛永元 | 1624年 | 福井二代藩主松平忠直、豊後(大分県)へ流罪となる | ||||||
| 2 | 1625年 | 府中の町数18町、戸数884戸 | ||||||
| 万治 3 | 1660年 | 加藤播磨、「模様入り鳥の子」を発明する | ||||||
| 寛文元 | 1661年 | 五箇村で福井藩の藩札を漉く | ||||||
| 5 | 1665年 | 越前奉書、「御上天下一」の印を許可される | ||||||
| 延宝 3 | 1675年 | 福井藩、五箇生産の奉書を他国へ出すことを禁じる | ||||||
| 6 | 1678年 | 福井藩、五箇に福井藩の御勘定所を置く | ||||||
| 貞享 3 | 1686年 | 貞享の大法により福井藩の領地半減、府中本多家の領地も2万石に半減 | ||||||
| 元禄 5 | 1692年 | 土岐頼殷、今立郡で2万5千石を領し、陣屋を野岡に置く | ||||||
| 10 | 1697年 | 紀伊松平頼職、高森に陣屋を置く | ||||||
| 12 | 1699年 | 福井藩、岩本村に紙会所を置き、判元制を採用する | ||||||
| 宝永 5 | 1708年 | 松ヶ鼻用水、洪水で大破する | ||||||
| 7 | 1710年 | 西鯖江陣屋代官古郡文右衛門、松ヶ鼻の護岸を完成させる | ||||||
| 正徳元 | 1711年 | 「府中総絵図」が描かれる 町数が31に増える | ||||||
| 5 | 1715年 | 越前和紙、倭漢三才図会で「越前鳥の子紙が紙の王にふさわしい紙」と評される | ||||||
| 享保 5 | 1720年 | 間部詮言、越後村上から鯖江に転封され、5万石の鯖江藩が成立する | ||||||
| 6 | 1721年 | 幕府の陣屋、西鯖江から本保へ移る | ||||||
| 7 | 1722年 | 享保の大火で粟田部の大半を焼失する | ||||||
| 元文元 | 1736年 | 本保陣屋を廃止し、公領は福井藩預かりとなる | ||||||
| 5 | 1740年 | 粟田部村の戸数333戸 | ||||||
| 延享元 | 1744年 | 再び本保に幕府の陣屋を置く | ||||||
| 宝暦 6 | 1756年 | 本保騒動が起きる | ||||||
| 12 | 1762年 | 4月の大火で府中の町のほとんどが焼失する | ||||||
| 明和 4 | 1767年 | 本保陣屋、飛騨郡代の支配となる | ||||||
| 元高山藩主金森家の一族金森左京が白崎に館を設ける | ||||||||
| 5 | 1768年 | 越前大一揆が起こる | ||||||
| 文化元 | 1804年 | 池ノ上町に恩沢池(灌漑用)完成する | ||||||
| 14 | 1817年 | 府中町の町数48町、戸数2,849戸 | ||||||
| 天保 3 | 1832年 | 鯖江藩の東庄境組・庄田組のうち480人が漆かきに他国へ出る | ||||||
| 4 | 1833年 | 蓑虫騒動が起こる | ||||||
| 7 | 1836年 | 天保の飢饉で多くの人が餓死する | ||||||
| 8 | 1837年 | 高山郡代大井永昌の徳をたたえ、本保に天保救荒碑が建立される | ||||||
| 9 | 1838年 | 府中町の戸数2,437戸 | ||||||
| 14 | 1843年 | 大滝神社の下宮本殿と拝殿を再建する | ||||||
| 弘化元 | 1844年 | 江戸城本丸焼失、福井藩は見舞品として五箇から鳥の子30万枚を贈る | ||||||
| 3 | 1846年 | 大暴風により粟田部で43戸潰れ、死者3人を出す | ||||||
| 嘉永 2 | 1849年 | 府中で初めて種痘が行われる | ||||||
| 5 | 1852年 | 嘉永の大火で、府中町の民家1,476戸が焼失する | ||||||
| 6 | 1853年 | 粟田部に藩校別館、郷学所「恵迪斉」を設立する | ||||||
| 7 | 1854年 | 五箇で丸岡藩札を漉く | ||||||
| 安政 3 | 1856年 | 藩校「立教館」を設立する 重野六十九、粟田部で蚊帳製造を始める | ||||||
| 文久元 | 1862年 | このころ、府中で蚊帳の製造を開始する | ||||||
| 元治元 | 1864年 | 府中医学所が新設される | ||||||
| 慶應元 | 1865年 | 福井藩、粟田部村本町に「制産役所」を置く | ||||||
| 近代 | 明治元 | 1868年 | 五箇で太政官札を漉く | |||||
| 2 | 1869年 | 府中を「武生」と改称する | ||||||
| 3 | 1870年 | 本多家華族に列せられず、武生騒動起こる 本保県が成立する | ||||||
| 4 | 1871年 | 福井県・鯖江県などが成立する | ||||||
| 5 | 1872年 | 武生郵便取扱所開設 | ||||||
| 進脩小学校など創立 | ||||||||
| 6 | 1873年 | 粟田部で大火、407戸焼失する 越前大一揆(ボロンカ騒動)起きる | ||||||
| 9 | 1876年 | 粟田部に繭市場開設する | ||||||
| 10 | 1877年 | 本山毫摂寺焼失、類焼100余戸に及ぶ | ||||||
| 11 | 1878年 | 明治天皇北陸行幸、引接寺が行在所となる 武生に南条・今立両郡役所を置く | ||||||
| 12 | 1879年 | 本多副元、華族に列せられる(1884年男爵となる) | ||||||
| 15 | 1882年 | 南越自由党結成する 粟田部村に先憂社を結成する | ||||||
| 29 | 1896年 | 北陸線森田まで開通する 武生駅営業開始する | ||||||
| 1897年 | ||||||||
| 31 | 1898年 | 福井県武生尋常中学校(旧制武生中学校)開校 岡本村に岡本製紙組合を設立する | ||||||
| 36 | 1903年 | 武生町大火、1,057戸焼失する | ||||||
| 39 | 1906年 | 町立武生女子実業学校開校する | ||||||
| 40 | 1907年 | 電話が開通する | ||||||
| 42 | 1909年 | 初めて電灯が灯る | ||||||
| 大正元 | 1912年 | 岡本村で製紙工がスト実施する | ||||||
| 2 | 1913年 | 武生町大火、481戸焼失する | ||||||
| 3 | 1914年 | 武岡軽便鉄道、五分市まで開通する | ||||||
| 9 | 1920年 | 第1回国勢調査、武生町人口18,068人 | ||||||
| 12 | 1923年 | 武生町立図書館落成する 紙祖神「川上御前」の分霊を抄紙局に祀る | ||||||
| 町立武生女子実業学校、県立武生高等女学校と改称する | ||||||||
| 13 | 1924年 | 南越鉄道、今立鉄道を合併し、戸の口(鯖江市)まで延長される | ||||||
| 14 | 1925年 | 福武電気鉄道、武生新から福井新まで開通する | ||||||
| 15 | 1926年 | 粟田部村、「粟田部町」となる | ||||||
| 昭和 2 | 1927年 | 粟田部町で大火、市街地のほぼ半数250戸が焼失する | ||||||
| 4 | 1929年 | 武生公会堂落成する | ||||||
| 15 | 1940年 | 大蔵省印刷局抄紙部出張所を岩本に設立する | ||||||
| 16 | 1941年 | 福武電気鉄道、南越鉄道を合併する | ||||||
| 19 | 1944年 | 大阪から疎開児童を受け入れる | ||||||
| 22 | 1947年 | 新制中学校発足する | ||||||
| 23 | 1948年 | 武生高等学校発足 武生町、神山村と合併し「武生市」が誕生する 人口31,743人 | ||||||
| 25 | 1950年 | 武生市、吉野・大虫・国高村を編入する | ||||||
| 26 | 1951年 | 武生市、坂口村を編入する | ||||||
| 27 | 1952年 | 第一回武生菊人形開催 | ||||||
| 29 | 1954年 | 武生市、王子保・北新庄・北日野村を編入する | ||||||
| 30 | 1955年 | 南中山村と服間村、粟田部町に合併される | ||||||
| 31 | 1956年 | 武生市、味真野村を編入 粟田部町を「今立町」に変更 岡本村、今立町に合併される | ||||||
| 33 | 1958年 | 武生トンネル(国道8号線)開通 | ||||||
| 34 | 1959年 | 武生市、白山村を編入する | ||||||
| 37 | 1962年 | 北陸トンネル(北陸線)開通、複線電化される | ||||||
| 38 | 1963年 | 三八豪雪 | ||||||
| 43 | 1968年 | 越前和紙職人八代目岩野市兵衛、重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される | ||||||
| 51 | 1976年 | 武生地方卸売市場落成する | ||||||
| 52 | 1977年 | 北陸自動車道武生から敦賀間開通される 旧谷口家住宅、城福寺庭園が重要文化財に指定される | ||||||
| 53 | 1978年 | 大塩八幡宮「拝殿」が重要文化財に指定される | ||||||
| 56 | 1981年 | 福井鉄道南越線の全線が廃線となる | ||||||
| 59 | 1984年 | 大滝神社下宮「本殿・拝殿」、重要文化財に指定される | ||||||
| 平成元 | 1989年 | |||||||
| 3 | 1991年 | 日野川に県下初の斜張橋が完成する | ||||||
| 6 | 1994年 | 大虫神社「木造男神坐像」、重要文化財に指定される | ||||||
| 7 | 1995年 | サンドーム福井完成する 「越前万歳」、重要無形民俗文化財に指定される | ||||||
| 12 | 2000年 | 越前和紙職人九代目岩野市兵衛、重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される | ||||||
| 16 | 2004年 | 福井豪雨により各地に大被害を受ける | ||||||
| 17 | 2005年 | 武生市と今立町が合併し、「越前市」となる | ||||||
越前国府のページはこちら